宮古島の今年の梅雨は6 月20 日に開けました。
なんと今年の梅雨は平年の約3 倍の降水量でした。
今年は水不足の心配はしなくてはいいかもしれません。
しかし数十年前まではどんなに雨が降っても水不足に陥っていました。
古来から宮古島は「非常に水の乏しい島」とされていました。
梅雨と台風で降水量は多いのに、水不足に苦しめられていました。
その要因は宮古島の土壌にあります。
宮古島の地層は2 つに分かれ、上の部分は琉球石灰岩というザルのような細かい穴が開いていて非常に水はけのよい地層、その下には島尻泥岩層という水を通しにくい地層です。
降った雨はすぐに石灰岩層を通り抜け、泥岩層にぶつかり、地下水となって海に流れてしまいます。
この地層のせいで宮古島には大きな川がありません。
川がないのでダムを造れず、水を貯めることができませんでした。
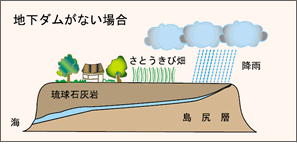
1971 年に歴史的な大干ばつが起きました。
これにより宮古島の農業は壊滅な打撃を受けました。
沖縄が日本に返還される前年のことです。
翌年の本土復帰をきっかけに、島人は国にダムや用水路などのかんがい事業を求めました。
そしてようやく1987 年に国営かんがい事業が着工されました。
このかんがい事業で中心となったのが、「地下ダム建設」です。
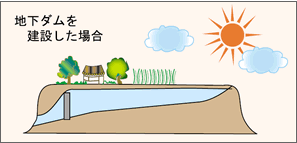
宮古島には川がないからダムを作れない。そこで作られたのが地下ダムです。
その名の通り、地下に水を貯めます。
水を通しにくい島尻泥岩層まで地上からコンクリートの杭を打ち、地下水が海へ流れ込むのをとめることで、無数の穴が開いている琉球石灰岩の中に水を貯めることができます。
水を含ませたスポンジをイメージするとわかりやすいと思います。
この地下ダムのおかげで宮古島の人々は水不足から解放されました。
地下ダムについては「宮古島地下ダム資料館」に様々な展示物があります。
ご興味がある方はぜひのぞいてみてください。おススメの施設です!
まだ問題はあります。
この地下水は、家庭で使うには非常に「硬い」のです。
琉球石灰岩層に水を貯めていると、水にカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが溶け込みます。
宮古島の地下水は日本国内の飲用水の上限近くの硬度があります。
髪を洗えばガビガビになり、やかんやお風呂の鏡にはミネラル(主にカルシウム) がこびりつき、お茶やコーヒーを淹れても美味しくない。

だから浄水場のろ過機で地下水の硬度を三分の一程度まで下げています。
そうすると浄水場では1 日当たり4 ~ 5 トンのミネラルの塊が採れるそうです。
それでもまだ硬度が高いので、ホテルや一部の家庭では軟水器を設置しています。
軟水器を通した水はとてもヌルヌルしていて石鹸水のような感触です。
宮古島の宿で手を洗うと「宮古にきたなー」といつも実感します。



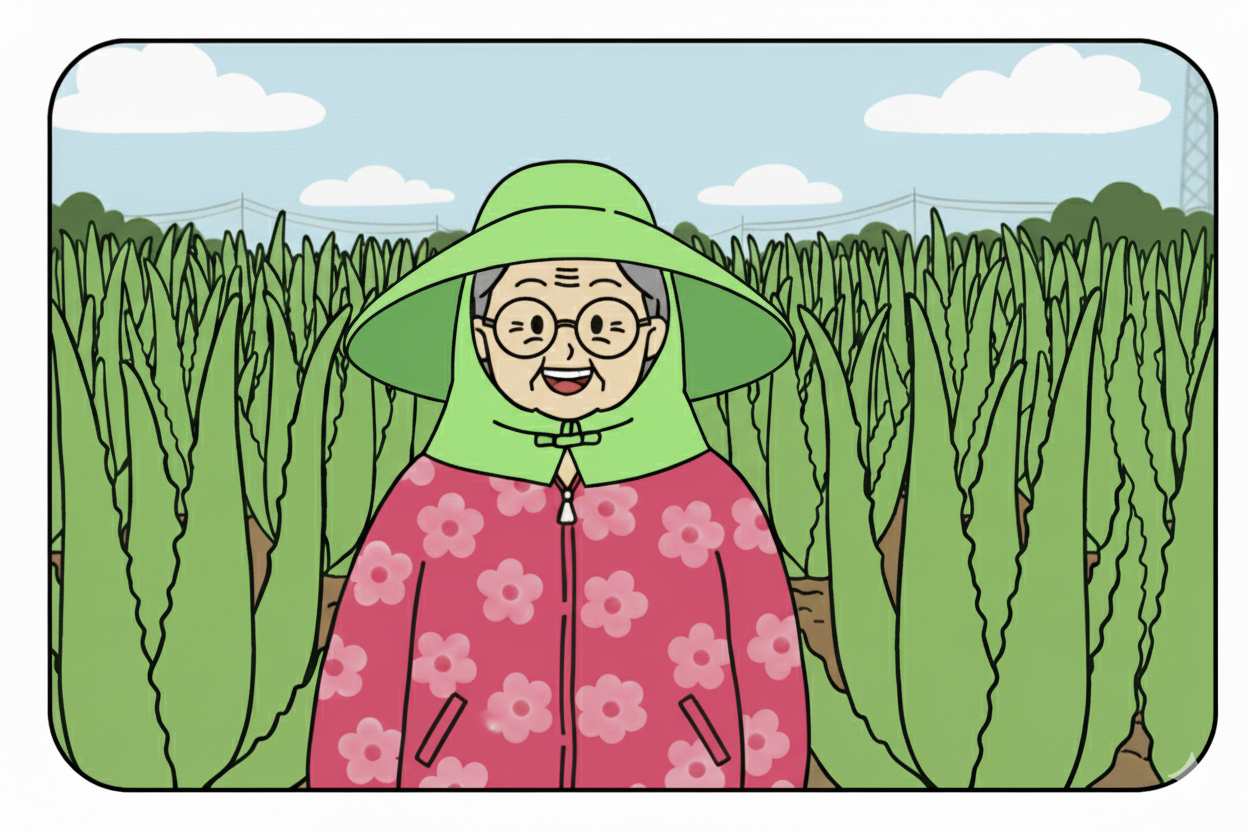
コメント